
「亀を飼うと貧乏になる」という言葉を耳にしたことはありますか。
古くからの言い伝えとして、まことしやかに囁かれるこのフレーズですが、実際に亀を飼おうと考えている方や、すでに飼育している方にとっては、気になる話かもしれません。
この記事では、亀を飼うと貧乏になると言われる背景にある、スピリチュアルな理由や言い伝えの真相を深掘りします。
また、風水の世界では亀がどのような存在として扱われているのか、金運や縁起との本当の関係性についても詳しく解説いたします。
さらに、迷信やイメージだけでなく、実際に亀を飼育する上で必要となる初期費用や年間の維持費、もしもの時の病気や治療費、そして長い寿命を持つ亀ならではの生涯コストといった現実的な側面にも焦点を当てていきます。
亀との生活がもたらす精神的なメリットや、飼い始める前に知っておくべき注意点まで、多角的な視点から情報をお届けします。
亀を飼うことが本当に経済的な負担につながるのか、それとも豊かな時間を与えてくれるのか、この記事を通して一緒に考えていきましょう。
- ➤亀を飼うと貧乏になると言われる言い伝えの背景
- ➤スピリチュアルな観点からの理由と解釈
- ➤風水における亀の縁起の良さと金運への影響
- ➤亀の飼育に必要なリアルな初期費用と維持費
- ➤長い寿命を持つ亀の生涯コストの考え方
- ➤万が一の病気に備えるための治療費の目安
- ➤言い伝え以上に大切な飼育前の心構えと注意点
亀を飼うと貧乏になるとの言い伝えが生まれた背景
- ■迷信が生まれたスピリチュアルな理由
- ■風水における亀の置物と飼育の考え方
- ■実は縁起が良い?金運アップの象徴とされる話
- ■亀を飼うことで得られる精神的なメリット
- ■言い伝えよりも大切な飼育前の注意点
迷信が生まれたスピリチュアルな理由

「亀を飼うと貧乏になる」という言葉は、多くの人が一度は耳にしたことがあるかもしれません。
この一見すると不思議な言い伝えには、いくつかのスピリチュアルな理由が背景にあると考えられています。
まず、亀の持つ「動かない」というイメージが関係しているようです。
亀は非常にゆっくりと行動し、あまり活発に動き回る動物ではありません。
この性質から、運気の停滞や気の流れの悪化を連想させ、結果として金運や財産が動かなくなり、貧しくなるという解釈が生まれたという説があります。
事業の発展や商売繁盛を願う人々にとって、物事が停滞するイメージは縁起が悪いと捉えられがちでした。
そのため、家の内に「動かない」象徴である亀を置くことは、家の運気そのものを停滞させるのではないかと懸念されたのかもしれません。
また、別の視点では、亀が「水」に関連する生き物であることも一因と考えられます。
スピリチュアルな世界観において、水は感情や潜在意識を象徴することがあります。
常に水の中にいる亀は、そうした感情のエネルギーを吸収しやすい存在と見なされることがありました。
もし家庭内に不和やネガティブな感情が渦巻いている場合、亀がその悪い気を吸い込み、家全体の運気を下げてしまうという考え方も存在します。
さらに、亀の長い寿命が逆説的に作用したという見方も興味深いものがあります。
長寿は本来喜ばしいことですが、一つのものが長く同じ場所にとどまり続けることを「執着」と捉える思想もあります。
つまり、亀を飼うことで家や財産に対する執着が強まり、新しい富や幸運が入ってくる流れを妨げてしまうのではないか、というわけです。
これらの理由は、いずれも科学的な根拠に基づいたものではなく、あくまで人々のイメージや思想から生まれた迷信の類と言えるでしょう。
しかし、こうしたスピリチュアルな背景を知ることは、なぜ「亀を飼うと貧乏になる」という言葉が現代にまで残っているのかを理解する上で、一つの手がかりになるのではないでしょうか。
風水における亀の置物と飼育の考え方
「亀を飼うと貧乏になる」という言い伝えがある一方で、風水の世界では亀はまったく異なる意味を持っています。
むしろ、亀は非常に縁起の良い、幸運を招くシンボルとして大切に扱われているのです。
風水において亀は、玄武(げんぶ)という天の四神(しじん)の一つに数えられます。
玄武は北方を守護する神聖な存在であり、硬い甲羅を持つことから「守り」や「安定」の象徴とされています。
そのため、家の北側に亀の置物を置くことで、災いや厄から家全体を守り、家族の健康や安定した生活をもたらすと考えられているのです。
この考え方は、生きている亀を飼育する場合にも応用されることがあります。
ただし、置物と生き物では、そのエネルギーの質が異なるとも言われます。
置物が静的で安定したエネルギーを放つのに対し、生きている亀は動的で成長するエネルギーを持つとされます。
そのため、生きている亀を飼う場合は、置物以上に強力な守護の力を発揮する可能性がある一方で、その飼育環境が運気に大きく影響すると考えられています。
例えば、水槽が汚れていたり、亀が不健康だったりすると、その悪い気が家全体に広がり、かえって運気を下げてしまうとされます。
これが、「亀を飼うと貧乏になる」という説と結びつく部分かもしれません。
つまり、風水的には亀そのものが悪いのではなく、不適切な飼育環境が問題を引き起こすというわけです。
逆に、清潔な環境で大切に飼育されている亀は、家のエネルギーを高め、住む人に幸運をもたらすと考えられます。
特に、仕事運や出世運を司る北の方角に水槽を置くと良いとされています。
亀がゆっくりと着実に歩む姿は、堅実な努力の積み重ねや、長期的な成功を象徴し、ビジネスの安定や発展を後押ししてくれるでしょう。
このように、風水の観点から見れば、亀は貧乏をもたらすどころか、むしろ家を守り、幸運を呼び込む強力なパートナーとなり得る存在なのです。
大切なのは、迷信に惑わされることなく、亀を尊重し、責任を持って飼育する姿勢だと言えるでしょう。
実は縁起が良い?金運アップの象徴とされる話

「亀を飼うと貧乏になる」という言葉とは裏腹に、亀は古来より世界中の多くの文化で縁起の良い生き物、特に金運アップの象徴として親しまれてきました。
日本においても、そのポジティブなイメージは数多くの昔話や言い伝えに見ることができます。
最も有名なのは「鶴は千年、亀は万年」という言葉でしょう。
この言葉が示す通り、亀は長寿のシンボルであり、健康で長く続く繁栄を意味します。
これは個人の健康だけでなく、家や事業が末永く続くことにも繋がり、結果的に財産の安定を象徴すると考えられています。
また、浦島太郎の物語では、亀を助けたお礼に竜宮城へ招かれます。
竜宮城は豪華絢爛で宝物に満ちた場所として描かれており、亀が富や豊かさへの案内役として登場している点は非常に興味深いところです。
このことから、亀は「幸運の運び手」としての役割も担っていると解釈できます。
さらに、亀の甲羅の形がお金(古銭)に似ていることから、直接的に金運と結びつけて考えられることも少なくありません。
甲羅の六角形の模様は「吉兆」を表す形とされ、非常に縁起が良いとされています。
このため、亀のモチーフの財布や置物を持つと、お金が貯まると信じられています。
ビジネスの世界でも、亀のイメージは好意的に捉えられます。
亀の着実でゆっくりとした歩みは、一攫千金を狙うのではなく、地道な努力を続けて大きな成功を収める「継続性」や「堅実性」の象徴です。
これは、安定した事業基盤を築き、長期的な繁栄を目指す上で非常に重要な資質と言えるでしょう。
古代中国の神話では、巨大な亀が世界をその背中で支えていると信じられていました。
このイメージから、亀は物事の「土台」や「基盤」を支える力を持つとされ、家や財産を守る守護神のような存在としても崇められてきました。
このように、世界的に見ても亀は富や長寿、幸運のシンボルとして扱われることの方が圧倒的に多いのです。
「亀を飼うと貧乏になる」という一部分の言い伝えに囚われず、こうしたポジティブな側面を知ることで、亀に対する見方も大きく変わってくるのではないでしょうか。
亀を飼うことで得られる精神的なメリット
金運や縁起といった側面だけでなく、亀を飼うことは私たちの心に豊かさをもたらしてくれます。
経済的な豊かさとはまた違う、精神的なメリットは、日々の生活に潤いと安らぎを与えてくれるでしょう。
まず挙げられるのは、その癒やし効果です。
水中をゆったりと泳ぐ姿や、陸地でのんびりと甲羅干しをする様子を眺めていると、不思議と心が落ち着きます。
現代社会の忙しい日常の中で、時間に追われがちな私たちにとって、亀の悠然としたたたずまいは、「急がなくても良いんだよ」と語りかけてくれているかのようです。
この穏やかな時間は、ストレスの軽減やリラックス効果に繋がることが期待できます。
次に、長期的なパートナーシップを築ける点も大きなメリットです。
前述の通り、亀は非常に寿命の長い生き物です。
種類によっては、人間の寿命を超えることも珍しくありません。
これは、飼い主にとって一生涯の付き合いになる可能性を意味します。
幼い頃から飼い始めれば、成長し、大人になり、そして年を重ねていく人生の様々なステージを共に過ごすことができます。
言葉を交わすことはできなくても、長年連れ添った亀は、飼い主にとってかけがえのない家族の一員、無言の親友のような存在になるでしょう。
この深い絆は、何物にも代えがたい精神的な支えとなります。
また、亀の飼育は、子どもたちの教育にも良い影響を与えます。
毎日のお世話を通して、生き物の命に対する責任感を学ぶことができます。
餌をあげたり、水を替えたりする中で、自分より弱い存在を思いやる心が育まれます。
さらに、亀の生態を観察することは、生命の神秘や自然環境への興味を引き出すきっかけにもなります。
なぜ甲羅があるのか、どうして冬眠するのかといった疑問から、自発的な学びへと繋がっていくことも少なくありません。
経済的な側面だけで物事を判断するのではなく、こうした精神的な豊かさ、つまりプライスレスな価値に目を向けることも、亀との暮らしを考える上では非常に大切です。
「貧乏になる」という言葉の裏側には、こうした心の充実という「富」が隠れているのかもしれません。
言い伝えよりも大切な飼育前の注意点
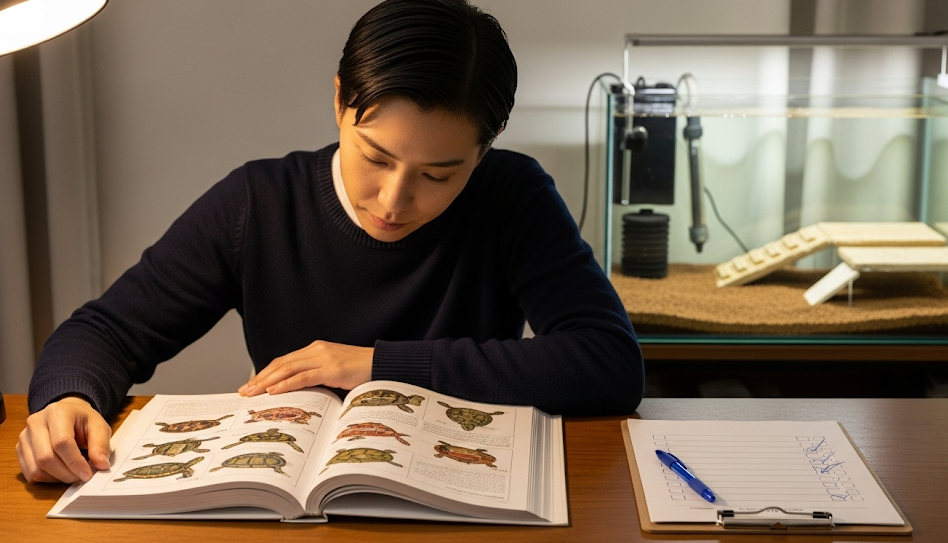
「亀を飼うと貧乏になる」という言い伝えが気になる気持ちも分かりますが、それ以上に重要で、真剣に考えなければならないのが、実際に亀を家族として迎え入れる前の準備と心構えです。
言い伝えはあくまで迷信ですが、準備不足は現実的な問題を引き起こす可能性があります。
最初に確認すべき最も大切なことは、その亀がどのくらいの大きさに成長するのか、そしてどのくらいの期間を生きるのかという点です。
ペットショップで小さくて可愛らしい姿で売られている亀も、種類によっては数年で人の顔ほどの大きさに成長することがあります。
また、寿命は数十年単位に及ぶことがほとんどです。
「こんなに大きくなるとは思わなかった」「自分の年齢を考えると、最後まで看取ることができない」といった理由で飼育を放棄することは、絶対にあってはなりません。
飼い始める前に、自分のライフプランと照らし合わせ、終生飼育が可能かどうかを冷静に判断する必要があります。
次に、適切な飼育環境を整えられるかどうかも重要なポイントです。
亀の種類によって、必要な水槽の大きさ、水温、陸地の有無、紫外線ライトの種類などが全く異なります。
例えば、水棲ガメとリクガメでは、必要な設備が根本的に違います。
こうした初期設備をしっかりと揃えるには、ある程度の費用がかかります。
安易に考えず、事前に必要なものをリストアップし、予算を確保しておくことが大切です。
また、日々の世話にどれくらいの時間と手間がかかるのかも理解しておくべきでしょう。
毎日の餌やりはもちろん、特に水棲ガメの場合は水換えが欠かせません。
水を清潔に保つことは、亀の健康を維持するために不可欠であり、これを怠ると病気の原因となります。
自分の生活スタイルの中で、定期的にお世話の時間を確保できるかどうかも、飼う前に考えておくべきことです。
最後に、万が一亀が病気になった場合に、診てもらえる動物病院が近くにあるかどうかも調べておくと安心です。
犬や猫と違い、爬虫類を専門的に診察できる獣医師は限られています。
いざという時に慌てないためにも、事前にエキゾチックアニマル対応の病院をリサーチしておくことを強くお勧めします。
これらの注意点を軽視してしまうことこそが、結果的に経済的、精神的な負担、つまり「貧乏」に繋がる本当の理由なのかもしれません。
言い伝えに心を惑わされるよりも、目の前の命に対する責任を真摯に受け止め、万全の準備をすることこそが、亀と幸せな生活を送るための第一歩となるでしょう。
亀を飼うと貧乏になる説とリアルな飼育費用
- ■水槽やライトなど飼育に必要な初期費用
- ■餌代や電気代といった年間の維持費
- ■万が一の際に備えるべき亀の病気と治療費
- ■長い寿命がもたらす生涯コストを考える
- ■まとめ:亀を飼うと貧乏になるかは準備次第
水槽やライトなど飼育に必要な初期費用

「亀を飼うと貧乏になる」という言葉には、実は現実的な費用の側面が隠されているのかもしれません。
亀を家族に迎えるにあたり、まず必要になるのが飼育環境を整えるための初期費用です。
この準備を安易に考えていると、後から出費がかさみ、経済的な負担を感じることになりかねません。
ここでは、代表的な水棲ガメ(ミドリガメなど)を例に、必要な初期費用を具体的に見ていきましょう。
- 水槽: 亀の成長を見越して、子ガメの時点でも最低でも60cm幅の水槽を用意するのが望ましいでしょう。価格は5,000円から15,000円程度が目安です。
- フィルター(ろ過装置): 水を清潔に保つために必須のアイテムです。水の汚れ具合に合わせて様々なタイプがありますが、3,000円から8,000円程度で選ぶことができます。
- バスキングライト(ホットスポット用): 亀が甲羅干しをして体温を調節するためのライトです。体を温める役割があり、2,000円から4,000円程度です。
- 紫外線ライト(UVB): カルシウムの吸収と骨の生成に不可欠なビタミンD3の合成を助けます。亀の健康維持に極めて重要で、3,000円から6,000円程度かかります。
- ヒーター: 冬場に水温を一定に保つために必要です。亀の活動を維持し、病気を予防します。3,000円から5,000円程度が相場です。
- 陸地(浮島): 亀が水から上がって甲羅干しをするためのスペースです。吸盤で固定するタイプなどがあり、1,500円から4,000円程度です。
- その他: カルキ抜き、水温計、隠れ家となるシェルター、底砂利など、細かな備品も必要に応じて揃えると、合計で3,000円から5,000円程度見ておくと良いでしょう。
これらの費用を合計すると、最低でも20,000円程度、こだわった設備を揃える場合は40,000円以上かかることが分かります。
これに、亀自体の生体価格(数百円から数千円)が加わります。
「ただ飼うだけ」と考え、水槽と餌だけを用意するのでは、亀は健康に生きていくことができません。
特に紫外線ライトやヒーターは、目に見えて効果が分かりにくいため軽視されがちですが、これらが不足すると、くる病などの深刻な病気を引き起こす原因となります。
最初にしっかりと投資をして適切な環境を整えることが、結果的に将来の治療費を抑え、亀と長く健康に暮らすための秘訣です。
この初期費用を「高い」と感じるか「必要経費」と捉えるか、そこに亀を飼う覚悟が表れると言えるかもしれません。
餌代や電気代といった年間の維持費
初期費用をかけて立派な飼育環境を整えた後も、亀との生活には継続的なコスト、つまり維持費がかかります。
「亀を飼うと貧乏になる」という言葉の背景には、このランニングコストの積み重ねが決して無視できない金額になる、という現実があるのかもしれません。
年間の維持費として主に考えられるのは、以下の項目です。
餌代
亀の主食となる配合飼料は、比較的安価で手に入ります。
成長度合いや種類にもよりますが、一般的な水棲ガメであれば、1ヶ月あたり500円から1,000円程度が目安となるでしょう。
ただし、栄養バランスを考えて、乾燥エビや野菜、種類によっては昆虫などを副食として与えることも推奨されます。
これらを含めると、年間で10,000円から15,000円程度を見積もっておくと安心です。
電気代
見落としがちですが、大きな割合を占めるのが電気代です。
亀の飼育には、主に3つの電化製品が稼働し続けます。
- フィルター: 24時間稼働させることが基本です。
- ヒーター: 特に秋から春にかけて、水温を一定に保つために稼働します。サーモスタット付きのものが一般的ですが、冬場は稼働時間が長くなります。
- 各種ライト: バスキングライトと紫外線ライトは、1日に8時間から10時間程度点灯させる必要があります。
これらの電気代を合計すると、飼育環境や季節によって変動はありますが、1ヶ月あたり1,500円から3,000円程度になることが多いようです。
年間では18,000円から36,000円となり、決して小さな金額ではないことが分かります。
消耗品の交換費用
飼育用品の中には、定期的に交換が必要なものもあります。
例えば、紫外線ライトのUVB照射能力は、約半年から1年で効果が薄れてしまうため、定期的な交換が必須です。
また、フィルターのろ材も、数ヶ月に一度の交換や清掃が推奨されています。
これらの交換費用として、年間で5,000円から10,000円程度を別途考えておく必要があります。
これらを総合すると、亀1匹を飼育するための年間の維持費は、おおよそ33,000円から61,000円程度となります。
月々に換算すると約2,750円から5,000円です。
一見すると大きな負担ではないように感じるかもしれませんが、これが数十年続くことを考えると、計画的に費用を管理していく必要があると言えるでしょう。
万が一の際に備えるべき亀の病気と治療費

「亀を飼うと貧乏になる」という言い伝えが、最も現実味を帯びるのは、おそらく亀が病気や怪我をした時でしょう。
ペットの医療費は、人間のような公的な健康保険が適用されないため、全額自己負担となります。
特に、亀のようなエキゾチックアニマルの場合、専門的な知識や設備が必要となるため、治療費が高額になる傾向があります。
亀がかかりやすい病気と、その治療にかかる費用の目安をいくつかご紹介します。
皮膚病・甲羅の病気(シェルロットなど)
不衛生な水質や、甲羅の乾燥不足、怪我などから細菌が感染して起こります。
甲羅の一部が変色したり、柔らかくなったり、穴が開いたりする症状が見られます。
初期段階であれば、患部の洗浄や消毒、抗生物質の軟膏塗布などで治療できますが、診察料と薬代で5,000円から15,000円程度かかることが一般的です。
症状が進行している場合は、より高額になる可能性もあります。
呼吸器感染症
不適切な温度管理や、体力の低下などが原因で発症します。
鼻水を出す、口を開けて苦しそうに呼吸するなどの症状が見られます。
抗生物質の投与が必要になることが多く、レントゲン検査や血液検査を行う場合もあります。
そうなると、治療費は20,000円から50,000円、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。
くる病(代謝性骨疾患)
紫外線(UVB)の不足や、カルシウム・ビタミンD3の欠乏によって骨が正常に形成されなくなる病気です。
甲羅が柔らかくなったり、手足が変形したりします。
治療には、飼育環境の大幅な見直し(紫外線ライトの設置など)に加え、カルシウム剤の投与などが行われます。
こちらも血液検査やレントゲン検査が必要になることが多く、治療が長期にわたるため、トータルで数万円の費用がかかることも覚悟しなければなりません。
こうした万が一の出費に備えて、ペット保険に加入するという選択肢もあります。
爬虫類を対象とした保険はまだ数は少ないですが、探せば見つかります。
あるいは、毎月数千円ずつでも「亀のための貯金」をしておくと、いざという時に経済的な理由で治療を諦めるという最悪の事態を避けることができます。
適切な飼育を心がけていれば病気のリスクは減らせますが、ゼロにすることはできません。
突然の数万円の出費が家計を圧迫し、「亀を飼ったせいで生活が苦しい」と感じてしまうことこそが、「貧乏になる」という言葉の正体なのかもしれません。
長い寿命がもたらす生涯コストを考える
これまで初期費用や年間維持費、そして医療費について見てきましたが、「亀を飼うと貧乏になる」という言葉の真の意味を理解するためには、これらを「生涯」という時間軸で捉える必要があります。
亀の最大の特徴は、その長い寿命にあります。
一般的にペットとして飼われるミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)でも、平均寿命は20年から30年、適切な環境で飼育すれば40年以上生きることもあります。
これは、一度飼い始めたら、大学進学、就職、結婚、子育てといった人生の大きなライフイベントを共に過ごす可能性が高いということです。
それでは、仮に亀が30年間生きると仮定して、生涯コストを計算してみましょう。
年間維持費の計算:
- 低めに見積もった場合: 33,000円/年 × 30年 = 990,000円
- 高めに見積もった場合: 61,000円/年 × 30年 = 1,830,000円
これに、最初の初期費用(約20,000円~40,000円)が加わります。
さらに、生涯で数回は病気や怪我で動物病院のお世話になる可能性も考慮すべきでしょう。
仮に、生涯で100,000円の医療費がかかったとします。
生涯コストの総額(試算):
生涯コストを合計すると、一匹の亀を終生飼育するためには、約110万円から200万円近い費用がかかる可能性があるという計算になります。
これは決して大げさな数字ではなく、非常に現実的な試算です。
もちろん、これは30年という長い期間にわたって支払われる金額であり、月々に換算すれば数千円の負担です。
しかし、総額として見ると、軽自動車が1台買えてしまうほどの金額になるのです。
この長期的な経済的コミットメントを理解せずに飼い始めてしまうと、将来的に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。
例えば、引っ越しが必要になった時、ペット可の物件が見つからなかったり、追加の費用が発生したりすることもあります。
また、飼い主自身が高齢になったり、病気になったりして、世話が続けられなくなる可能性もゼロではありません。
「亀を飼うと貧乏になる」という言葉は、単に目先の出費を指すのではなく、この数十年単位の長い付き合いの中で発生する、予期せぬ出費や生活の変化に対する備えがなければ、経済的にも精神的にも追い詰められるリスクがある、という先人からの警告なのかもしれません。
亀を飼うことは、この長い時間と責任を共に引き受ける覚悟が問われるのです。
まとめ:亀を飼うと貧乏になるかは準備次第

ここまで、「亀を飼うと貧乏になる」という言葉の背景にあるスピリチュアルな言い伝えから、風水における縁起、そして非常に現実的な飼育費用まで、様々な角度から掘り下げてきました。
結論として言えるのは、亀を飼うと貧乏になるかどうかは、迷信や縁起で決まるのではなく、すべて飼い主の「準備」と「覚悟」にかかっているということです。
言い伝えや迷信は、科学的根拠のない、あくまで古くからの人々のイメージの産物です。
むしろ、風水や多くの文化では、亀は長寿や守護、金運の象徴とされる幸運の生き物です。
したがって、スピリチュアルな意味で貧乏になることを心配する必要はほとんどないと言えるでしょう。
一方で、この言い伝えが現代にも通じる「真実」の一面を持っているとすれば、それは経済的な側面です。
初期費用、年間の維持費、そして万が一の医療費。
これらを積み重ね、さらに20年、30年という長い寿命で掛け合わせると、生涯コストは決して安価なものではありません。
この長期的な費用と責任を理解せず、安易な気持ちで飼い始めてしまえば、予期せぬ出費が家計を圧迫し、結果として「亀のせいで生活が苦しい」と感じる状況、つまり「貧乏になった」と感じる事態を招きかねません。
しかし、これは亀に限った話ではなく、犬や猫を含め、ペットと暮らす全てのケースに共通して言えることです。
事前に必要な知識を学び、費用を計画し、終生飼育する覚悟を持って迎え入れるならば、亀は経済的な負担を上回るほどの、計り知れない癒やしと喜び、そして精神的な豊かさを与えてくれる存在になります。
それは、お金では決して買うことのできない「心の富」と言えるでしょう。
最終的に、亀を飼うと貧乏になるのではなく、「準備不足のまま亀を飼うと、経済的にも精神的にも貧しくなるリスクがある」というのが、この言葉の現代的な解釈なのかもしれません。
これから亀を迎えようと考えている方は、どうか言い伝えに惑わされず、目の前の命と真摯に向き合い、万全の準備を整えてください。
そうすれば、亀はきっとあなたにとって最高のパートナーとなってくれるはずです。
- ➤「亀を飼うと貧乏になる」は主に迷信や言い伝えが発端
- ➤亀の不動のイメージが運気の停滞を連想させたとされる
- ➤一方で風水では亀は守護と安定の象徴で縁起が良い
- ➤金運アップのシンボルとして扱われる文化も多い
- ➤亀の飼育には精神的な癒やしというメリットがある
- ➤言い伝えより飼育前の現実的な準備が何より重要
- ➤飼育には水槽やライトなどの初期費用がかかる
- ➤初期費用の目安は2万円から4万円以上と幅がある
- ➤餌代や電気代などの年間維持費も継続的に発生する
- ➤年間維持費は3万円から6万円程度が目安となる
- ➤病気や怪我の治療費は高額になる可能性がある
- ➤亀の寿命は数十年と非常に長く長期的な視点が必要
- ➤生涯コストは100万円を超えることも珍しくない
- ➤貧乏になるかは飼い主の計画性と覚悟次第である
- ➤十分な準備をすれば亀は人生を豊かにするパートナーになる









